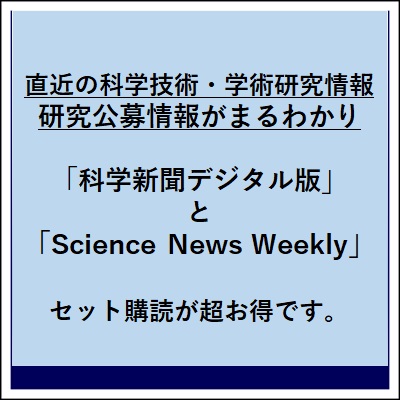役に立つ研究ではなく、役に立たない研究をやることが研究者にとって素晴らしいことだとか、重要だとか。そんな議論を最近、聞くことがあった▼自然科学の成立過程を見ていくと、古代のアリストテレスらの哲学から始まり、中世ではキリスト教世界における神の意図を理解するための神学を経て、18世紀に現代的な科学が成立した。いくつかの学校ができたことで、その知識が閉じられた世界から、広く社会に流通するようになった▼古代では暇を持て余す人たちが観察・思索・考察することで知識を生み出し、中世では、教会や貴族など、時間とお金に余裕のある人たちが主役であった。そういう人たちにとって、役に立つとか立たないとかという課題設定は意味を持たなかったのではないだろうか▼20世紀になると、ハーバーボッシュ法が発明され、人類の食糧生産能力は大きく向上し、量子力学は現代社会の基盤を形成している。進化した天文学は宇宙の理解に役立っている。挙げればきりがないほど、役に立つ科学で満ちあふれている▼四半世紀以上前、電子工学者の故・猪瀬博先生と学術研究とはなにかという話をして、「内在的欲求に基づく研究である」という一定の結論を得た。内在的欲求は、具体的課題を解決したい、真理を探究したいなど、人それぞれであり、内容によって優劣をつけることはできない。偶然、社会的課題と一致すれば研究資金が集まることがある▼近年、政府の設定する目標を達成するための研究費が増える一方、基盤的な経費は厳しくなり、研究現場には余裕がない。しかし、問題の本質を偽ることは、自らをだますことになり、研究への姿勢そのものをゆがめることになりかねない。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS