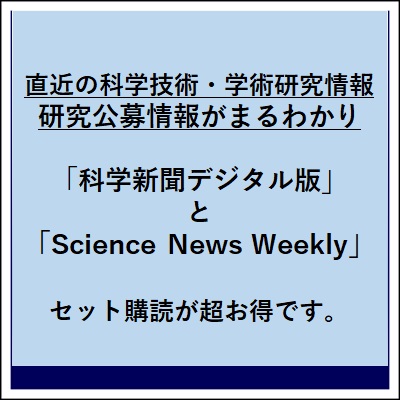素領域
科学新聞の1面に掲載している『素領域』全文と、Web限定コラムをお読みいただけます。
2026年2月6日号 素領域
子宮頸がんには、腺がんと扁平上皮がんがある。腺がんは検診で見つかりにくく、早期発見が難しい上、転移も多く、死亡につながるケースが多い。ただし、ワクチンによって子宮頸がんの9割以上を予防できる可能性がある▼HPVワクチンは2013年から定期接種になったが、有害事象の報道が相次ぎ、わずか2カ月で積極的推奨が控えられ、接種率はほぼゼロになった。20年頃から一部自治体で定期接種が再開され、22年4月からキ…
2026年1月30日号 素領域
21世紀に入ってから今年で26年目を迎えた。もう四半世紀が過ぎたことになる▼しかし、ウクライナとロシアの紛争は続いており、イスラエルとガザは停戦したものの、ガザ地区は紛争で荒廃したままだ▼世界的な異常気象をもたらしている地球温暖化問題への対策も進んでおらず、世界のCO2排出量は今も増え続けている。加えて、米国トランプ大統領が世界をひっかき回している▼中南米やグリーンランドなどをめぐり、新たな国際的…
2026年1月23日号 素領域
昨年8月に沖縄美ら島財団と東京大学などの研究グループは、沖縄本島東沖の水深約900㍍の深海で新種のサンゴ「リュウキュウサンゴ」を発見し、話題になった。いわゆる宝石サンゴの仲間で、サンゴ礁を形づくるものとは異なるグループに属し、生態も全く異なる▼造礁サンゴは主に褐虫藻と共生し、光合成で生きているが、宝石サンゴは主に光が届かない冷たい深海でプランクトンを餌に生きている。生殖様式も異なり、宝石サンゴは雌…
2026年1月16日号 素領域
毎年、世界で230万人が乳がんに罹患しており、国内でも年間約10万人の新規患者が生まれている。早期乳がん治療の第一選択肢は手術による切除であり、多くの患者が乳房の一部または全部を切除する。最近では乳房温存療法も広がってきたが、手術による傷跡や変形などもあることから、手術そのものを望まない患者も多い▼重粒子線を使ったがん治療は、がん病巣に集中して高い線料を届け、周囲の正常組織に当たる線量を低くできる…
2026年1月9日号 素領域
最近、防災関連の話で「フェーズフリー」ということばをよく耳にするようになった。一般社団法人フェーズフリー協会という団体が2018年に発足している▼そのホームページには、14年にスペラディウス代表の佐藤唯行氏(同協会代表理事)がこれを提唱、このことばを、平常時に利用されるすべての商品とサービスが持つ、災害時に役立つ付加価値だと定義したとある▼平常時や災害時という2つのフェーズの制約から自由であること…
2026年1月1日号 素領域
明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします▼正月には餅の誤嚥にご注意を。消費者庁が2018年と19年の2年間を分析したところ、気道閉塞を生じた食物の誤嚥のうち、65歳以上の餅による窒息事故の死亡者数は18年が363人、19年が298人で、事故発生は43%が1月に集中していた▼餅は温度が下がるに従い硬さと付着性が増す性質があり、喉を通る時には温度が下がりくっつきやすくなると…
2025年12月19日号 素領域
今年最後の号となりました。読者の皆さまには、来年が良い年となるよう祈念しております▼今年はクマのニュースが全国的に話題になり、日本漢字能力検定協会が発表した今年の漢字は「熊」になりました。クマによる被害は、地球温暖化による植生の変化や耕作放棄地拡大に伴う里山の減少など、様々な要因が考えられています。こうした状況だからこそ、フィールドワークを含む地道な研究活動がますます重要になると思います▼一般公募…
2025年12月12日号 素領域
今年も師走に入り、残すところ3週間程度になったので、振り返って雑感を記したい▼温暖化の影響で今年の夏も大変な暑さだった。しかし、10月に入ると急速に気温が下がり、涼しさを通り過ぎて寒い日が続くようになった。また、東北や北海道を中心に各地でクマが市街地などに出没し、人を襲う事案が多発している。科学分野では二人の日本人のノーベル賞受賞があって明るい話題となった▼注目のAIは開発や利用が進み、様々な分野…
2025年12月5日号 素領域
大分市佐賀関で11月18日夕刻に発生した火災は、市消防局によれば28日に半島側で鎮火し、飛び火したとみられる約1・5㌔㍍離れた蔦島は鎮圧を確認。半島側では引き続き警戒巡回を行い、蔦島ではドローンによる熱源探査を行っていくという。この火災で死者1人、軽傷者1人、建物被害182棟の被害が出た。鎮圧とは火災拡大の危険がなくなった状態、鎮火は再燃のおそれがない状態を意味し、いずれも現場最高指揮者が認定する…
2025年11月28日号 素領域
第7期科学技術・イノベーション基本計画では、どのような研究領域に重点がおかれるのか。先日開催された、基本計画専門調査会の下のワーキンググループでは、造船、航空・宇宙、サイバーセキュリティなど10の新興・基盤技術領域、AI・先端ロボット、量子、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギーなど6つの国家戦略技術領域が示された▼新興・基盤技術領域については、各府省の予算で柔軟に支援していき、国家戦略技術領…
2025年11月21日号 素領域
国際通信を支える光海底ケーブルの損壊が、近年日本周辺で増えており問題になっている。その対策のため総務省が「国際海底ケーブルの防護等に関する研究会」を先日開催した▼海底に敷設される光ケーブルは、最大8000㍍もある深い海溝もまたいで設置されるので、水圧などに耐えるようにポリエチレン樹脂や銅パイプなどでしっかり保護されている。それでも、世界では100から200件程度の破損などによる障害が毎年発生してい…
2025年11月14日号 素領域
11月は霜月ともよばれ、二十四節気では11月7日頃から12月6日頃までが初冬になる▼気象庁は今年度の冬シーズンから初霜・初氷の目視観測を終了した。アメダスや衛星など最新の技術による客観的かつ定量的な情報が提供できるようになったことを受けての見直しだという。これまでは全国の気象台や測候所の露場(ろじょう)を観測点にして職員の目視で行われていた。露場とは周囲の人工物の影響を受けないよう配慮した観測装置…
2025年11月7日号 素領域
先日、第5回医療等情報の利活用の推進に関する検討会が開かれた。有効な治療法・医薬品・医療機器等の開発による医療の質の向上、医療資源の最適配分などにつなげるため、患者の医療情報の二次利用に関する基本理念や制度の枠組みなどを検討している▼疫学研究者、患者団体、法律家からヒアリングが行われたが、ある委員が「どうしてマイナンバーカードと医療情報を結びつけてはいけないのか」と質問した。法律家からは、医療情報…
2025年10月31日号 素領域
高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に選出され、日本初の女性首相誕生に世の中の期待感が高まっている。就任後の記者会見でも意気込みを感じる。その高市首相が初閣議で示した基本方針では「強い経済の実現」「地方を伸ばし、暮らしを守る」「外交力と防衛力の強化」を掲げた▼今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。日本と日本人の底…
2025年10月24日号 素領域
キンモクセイは秋に甘い香りを漂わせる橙色の小さな花を数㌢㍍の塊状に咲かせる常緑小高木で、庭の植栽として親しまれている。しかし少し調べてみると親しまれている割に不明なことの多い植物だ▼属名の「Osmanthus(オスマンサス)」はギリシャ語の「osme(香り)」と「anthos(花)」が語源で、和名はギンモクセイの花が白であることから、橙色を金にたとえて名付けられたらしい▼中国原産の雌雄異株で、日本…
2025年10月17日号 素領域
今年は2人の日本人がノーベル賞を受賞した。非常に喜ばしいことだ。しかし、基盤的経費が削減され、それと比較して科研費の伸び率は低く、特定目的のための研究費は増加してきた。さらに大学改革などのための各種競争的資金が雨後の筍のように次々とできては消えていき、申請や評価のために研究者の研究時間は大きく削られており、次のノーベル賞級の成果を生み出すための土壌は脆弱だ▼生理学・医学賞の坂口志文博士、化学賞の北…
2025年10月10日号 素領域
AIの進化は一層加速しており、創造的なコンテンツ作成などができる生成AIから、いまや自ら課題を見つけて解決し意思決定するエージェンティックAIへと進化している▼そうしたAIと、それが与える脅威について先日、IEEEオンラインプレスセミナーでの講演を聴いた。講師は九州大学の櫻井幸一教授である。講演「AIの進化と脅威:人工知能が地政学を変える時代のサイバーセキュリティ」では、実際の事例などをあげて脅威…
2025年10月3日号 素領域
今年のイグ・ノーベル賞授賞式が米国マサチューセッツ州のボストン大学で開催され、10の個人または研究グループが受賞した。同賞は「人を笑わせ、そして考えさせる」研究などに毎年贈られている▼日本で行われた研究は同賞の常連で、今年も「シマウマのようなしま模様を描いたウシが吸血性のサシバエ類に刺されないようにできるかを調べる実験を行った」ことで愛知県農業総合試験場畜産研究部の兒嶋朋貴氏(現在は農研機構畜産研…
2025年9月26日号 素領域
科学技術・イノベーション政策は、国家安全保障政策とどのような距離感で連携すべきなのか▼基本計画専門調査会で、上山隆大・前CSTI議員は、国家安全保障が第7期基本計画の重要な軸になるという考えを示したうえで「ハイリスクマネーである安全保障系の資金をイノベーション政策にどう取り込んでいくのかが、これまでの基本計画のミッシングポイント」と説明した。米国では1990年代に安全保障系の資金がハイリスクな研究…
2025年9月12日号 素領域
デジタル時代の学生(対象は全国の18歳から29歳の学生)に対し読み書きの実態を調査した結果が、9月1日に公表された▼これは、一般社団法人応用脳科学コンソーシアム(CAN)や東大、NTTデータ経営研究所など7機関・企業が共同で実施した、筆記と読書の関係性を科学的に検証する調査だ▼その結果として示された中で気になったのは、大学などの講義内容を手書きや電子機器で記録する人や、本や新聞・雑誌を普段読む人の…
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS