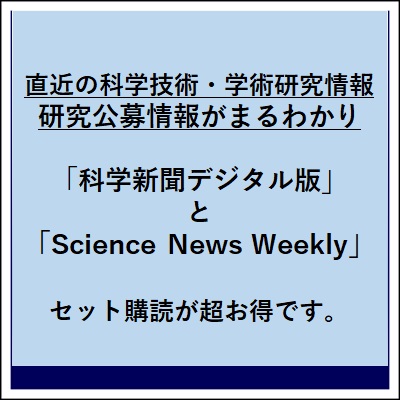沖縄本島地域を中心に、海外から侵入したセグロウリミバエの発生が確認され、現在当該地域では植物防疫法に基づく不妊虫の放飼を含む緊急防除が行われている▼セグロウリミバエは成虫の体長が8~9㍉㍍、体色が黒と橙色の昆虫で、昨年3月に沖縄本島北部で確認された。過去2度にわたり沖縄県の調査用誘引トラップで発見されたことがあるが、寄生果実が確認されるなどの国内における発見は今回が初めてだという▼セグロウリミバエは東アジアや東南アジアに広く分布し、ウリ科植物を中心に広く生果実を加害し、被害はパパイヤやトマトなどにも拡大。現在多くの植物の県外への持ち出しが禁止されているほか沖縄県内の家庭菜園等での栽培の自粛が要請されている。海外の事例ではあるが発生状況により収穫量80%減も報告されている。かつて沖縄に甚大な被害を及ぼしたウリミバエと同じミバエ科の害虫で、幼虫が果実に寄生すると腐敗・落果する▼ウリミバエは1993年に根絶された。ウリミバエの根絶防除事業は1972年の沖縄の本土復帰事業として久米島で着手されてから根絶まで約22年、約204億円の費用を要した。根絶までに652億頭の不妊虫が放飼されたという。現在でも植物防疫所と都道府県が連携して県全域に誘引トラップが設置され調査は継続。侵入が警戒されている▼沖縄県の農業生産に甚大な被害が生じるだけでなく同県の経済への影響が懸念される。過去のウリミバエでは放飼された不妊虫が海上を200㌔㍍移動したことが確認されている。対岸の火事と思わず、グローバリゼーションに伴う対策の強化を期待したい。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS