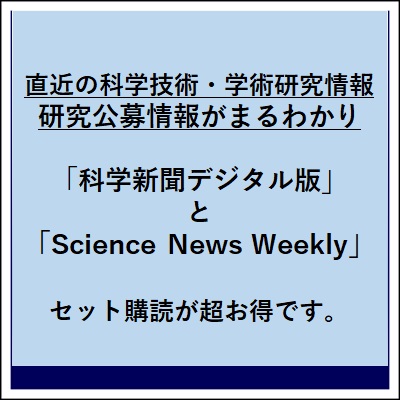科学技術・イノベーション政策は、国家安全保障政策とどのような距離感で連携すべきなのか▼基本計画専門調査会で、上山隆大・前CSTI議員は、国家安全保障が第7期基本計画の重要な軸になるという考えを示したうえで「ハイリスクマネーである安全保障系の資金をイノベーション政策にどう取り込んでいくのかが、これまでの基本計画のミッシングポイント」と説明した。米国では1990年代に安全保障系の資金がハイリスクな研究開発投資に投じられ、さらにリーマンショックで民間資金もテクノロジー系ベンチャーへの投資に向いたことを理由にあげている。しかし、別の委員からはリーマンショックがあったからこその事象で、同じことは日本では起こらないだろうと指摘している▼先日、防衛省関係の人たちと話をする機会があった。米国から戦闘機を買う予算はあるが、普通の弾薬や自衛隊の装備(衣服等)の予算には余裕がなく、令和の米騒動で米価が高騰すると、おかわり自由だった食堂に制限が導入されたことなど、厳しい実情を知った。基盤的経費と競争的資金の関係を思い起こさせる▼米国の国防予算は年間約100兆円強の規模で、日本の防衛予算は2025年度には9・4%と大幅に上がったものの8兆7005億円と12分の1程度。またDARPA予算は24年度では約6000億円なのに対して、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンディング)には、毎年100億円程度だ▼もともとの投資規模が違うことに加えて、米国の国防予算の多くは自由裁量経費で構成されているという予算構造の違いもある。安全保障との連携の議論をする前にシステムを変える努力をすべきだろう。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS