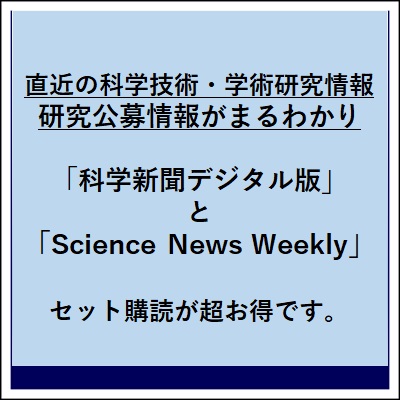AIの進化は一層加速しており、創造的なコンテンツ作成などができる生成AIから、いまや自ら課題を見つけて解決し意思決定するエージェンティックAIへと進化している▼そうしたAIと、それが与える脅威について先日、IEEEオンラインプレスセミナーでの講演を聴いた。講師は九州大学の櫻井幸一教授である。講演「AIの進化と脅威:人工知能が地政学を変える時代のサイバーセキュリティ」では、実際の事例などをあげて脅威の現状などを紹介した▼例えば生成AIが学術団体に与える危険性では、いたずら・愉快犯による不良論文の投稿や、実際の研究者をかたった偽論文投稿の存在をあげた。AIが執筆した研究論文が、実際に査読を受けてAI系トップ国際会議で採択された例が複数も報告されていることも紹介した。まさに生成AIのすごさが分かる事例だと感じた▼その一方で、AIには未知の内在的特性があることが分かってきており、AIの学者やエンジニアが探求しているが、ハッカーがこの脆弱性を先に利用してゼロデイ攻撃する危険性があるという懸念も示した。さらに、AIの活用は国家間の地理的距離の意味を変質させ、AI兵器は、核に代わる新たな国家戦略になるという考察(宮家邦彦氏)があることを紹介した▼以前、本欄でAIは核より怖い武器になると書いた覚えがあるが、すでにそうした動きが世界の水面下で進みつつあるようだ。「人間は考える葦である」とは17世紀のフランスの哲学者パスカルの言葉だ▼人間が考えることの重要性を説いたもので、これを安易な発想で全面的にAIに任せてしまっていいのかと心配になる。その開発や社会実装には深い思慮が欠かせないと、講演を聴いてあらためて思った。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS