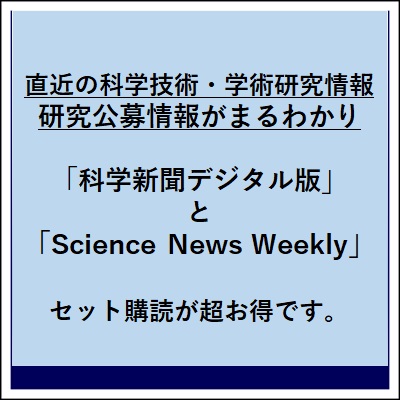国際通信を支える光海底ケーブルの損壊が、近年日本周辺で増えており問題になっている。その対策のため総務省が「国際海底ケーブルの防護等に関する研究会」を先日開催した▼海底に敷設される光ケーブルは、最大8000㍍もある深い海溝もまたいで設置されるので、水圧などに耐えるようにポリエチレン樹脂や銅パイプなどでしっかり保護されている。それでも、世界では100から200件程度の破損などによる障害が毎年発生している。最も多い原因は海底引き網などの漁業活動(約4割)だという▼さらに船舶の錨によるもの、海賊による切断などを合わせて人為的な原因が6割を占めている。自然災害によるものも1割程度ある。日本周辺の海底には多くの光ケーブルが敷設されているが、その地形的特徴から損壊事故が集中している。今後の国際海底ケーブルの増加にともない、こうした損壊事故の一層の増加が懸念される▼いまやインターネットは世界を結ぶ重要なサービスである。これを支える国際海底ケーブルもまた、世界中の国や人々にとって必要不可欠なインフラである。まして、今後は利用が急拡大する見通しにあるAI。運用するデータセンターの建設も世界中で加速している。しかし、それらをつなぐインフラの事故が多くては、AI普及の支障にもなりかねない▼総務省研究会では今後、国際海底ケーブルや陸揚げ局の防護体制強化や監督体制・連携体制の強化などを議論し、来年8月ごろに報告書をまとめる予定だ。議論の行方を見守りたい。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS