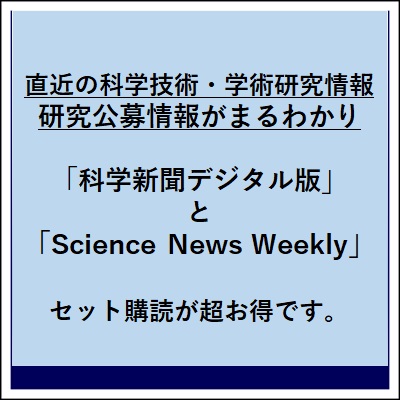警視庁によれば昨年の水難事故は1535件で前年度と比較して143件増加し、過去10年間で最多となった。死者・行方不明者も816人と前年度から73人増加している。水難事故は昭和50年には4千5百件以上発生していたが、以降減少傾向が続いていた。一方で近年は減少が頭打ちで、ここ数年間は微増している▼発生場所は海が約46%、河川が約35%。行為別では魚とり・釣りが最も多く約23%、次いで作業中約8%となった。よく子供の水難事故が報道されるので未就学児や児童生徒が多いのかと思いきや、中学生以下は約11%だ▼防止対策として、魚取り・釣りでは転落等の恐れがある場所や水草・海藻が繁茂している場所、水温の変化や水流の激しい場所には近づかないことや、気象情報を把握すること、ライフジャネットを正しく着用することなどがあげられる▼(公財)河川財団によれば河川と海では水難事故の傾向が異なるという。同財団は河川や湖沼での事故を防ぐためのポイントをまとめた「水辺の安全ハンドブック」を公開している。人が空気を肺に吸い込んだ状態では真水でも体は水に浮くものの、たとえ仰向けで浮かんでも流れのある川でその姿勢を保つのは困難で、浮く力が足りないと川底方向へと沈んでいく。川底の石の間等に足が挟まれると、流れが速ければライフジャケットを着ていても動水圧で水中に体が押し込まれトラップされるという▼とはいえ海や川は様々な生物にあふれ、親しむ経験は無駄にはならない。お出かけ前に「水難事故マップ」などで危険な場所をチェックしてみてはいかがだろうか。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS