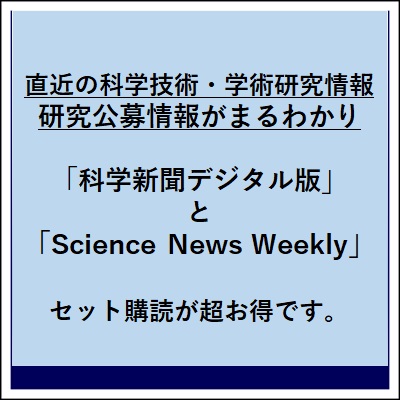先日、農研機構の大豆ゲノムに関する記者会見の後、圃場ではなく一本ずつ、遺伝情報の異なる交配品種を調べれば、収量の高いものを見つけられるのではないかと思って聞いてみた。答えはノーだった。実はその研究者も世界的種苗会社に同じ質問をしてみたことがあるという▼農作物の収量には様々な要素が関わっている。例えば、さやが弾けやすいとコンバインで収穫するときに豆だけが取り残され、それだけで2割も収量が変わる。また、集団としての倒れやすさや気象変化への強さなどは、単体ではわからないため、圃場規模で育てる必要がある▼化学合成の世界では、実験室で高い収率などを達成しても、大量生産のため規模を拡大する際、実験室とは異なる様々な条件をクリアしなければならないことが多い▼ことほど左様に、研究室と現実問題の間には高い壁や深い溝が存在している。それをつなげることがイノベーションであり、その手段の一つがスタートアップ創出と言えるだろう。その根底には、この問題を解決して生産性を上げたい、生活を豊かにしたい、この病気を治して患者さんを助けたいという情熱がある。しかし、近年のスタートアップ政策を見ていると手段であるはずの起業が目的化しているかのような印象を受ける▼こうした目的と手段が逆転した事例は他にもある。例えば、労働契約法の無期転換だ。現場を知らない人たちが理想論だけで作ったため、雇用が安定化するどころか不安定になり、多くの問題を発生させてしまっている。理想と現実の狭間は階層構造になっており、また多くの要素を含んでいる。政策や法律、ルールを作る側には思慮が求められる。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS