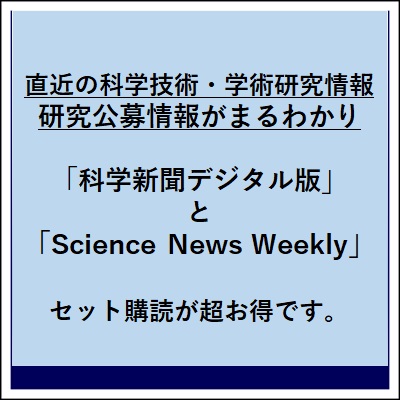国土交通省は8月1日に「令和7年版日本の水資源の現況」を公表した▼地球上には約14億立方㌔㍍の水が存在すると考えられているが、このうち淡水は2・5%程度しかない。そのうえ淡水の多くは南極や北極地域などの氷として存在し、それを除くと0・8%。そこから地下水を除いた、人が利用しやすい淡水は約0・01%(10万立方㌔㍍)しかない▼日本は世界でも降水量が多い国で、その量は世界平均の2倍ではあるが地域によりばらつきがあり、北海道、東北、関東内陸、関東臨海部、山陰では全国平均を下回っている(1992~2021年の平均)。そのため毎年いずれかの地域で渇水が生じ、94年には大渇水が起きた▼国土交通省によれば渇水とは河川の管理を行うに当たり、河川からの取水を通常通り継続するとダムの貯水が枯渇すると想定される場合等に取水制限を行うなど、利水者が平常時と同様の取水を行うことができない状況だという▼今年も7月30日に国土交通省渇水対策本部が設置され、地域の渇水による被害を最小限にするため国土交通省所有機器の活用等の対策が通知された。九州では現在も筑後川局渇水対策本部を設置。筑後川流域では今年7月の雨量が平年の1割程度しかなく、ダムの貯水率が低下していることから節水を呼びかけている▼今年は四国・吉野川水系の新宮ダム(愛媛県四国中央市)が管理50周年を迎え、記念にダム湖名の募集が10月24日まで行われている。渇水に見舞われている筑後川水系の江川ダム(福岡県朝倉市)も管理50周年を迎え、50周年ロゴシール付きダムカード(国土交通省と水資源機構の管理するダムで配布)と水の恵みカード(農林水産省が各所で配布)の作成も行っているという▼水の恵みに感謝すると共に、夏休みのお出かけにダム見学もいいかもしれない。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS