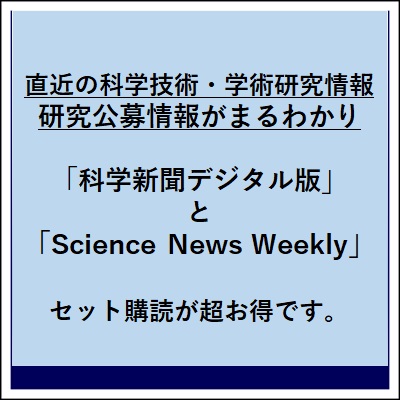デジタル時代の学生(対象は全国の18歳から29歳の学生)に対し読み書きの実態を調査した結果が、9月1日に公表された▼これは、一般社団法人応用脳科学コンソーシアム(CAN)や東大、NTTデータ経営研究所など7機関・企業が共同で実施した、筆記と読書の関係性を科学的に検証する調査だ▼その結果として示された中で気になったのは、大学などの講義内容を手書きや電子機器で記録する人や、本や新聞・雑誌を普段読む人の方が国語の成績が高かったことである。日常的なメモの取り方や読書習慣は、文章の読解力や論理的な思考力に関係するということが明確に示されたとしている▼ところで、世の中でいま盛んに進められているデジタル化(DX)は、効率化、便利さなどを追求したものだと言える。企業だけでなく行政・研究・教育・文化・報道機関、さらには家庭など、様々な分野でデジタル化が進んでいる。しかし、本来はアナログな生き物である人間の活動にとって、すべてデジタル化されることが本当に適切なのかはまだ分からない。現在のDXは、大半は経済面から追求した人間活動のデジタル化であって、人間の知的活動や生理的な面などから追求したとは言い切れない部分もある▼先述の実態調査は、デジタルとアナログの効果の良し悪しを調べたものではない。しかし、少なくとも紙への手書きや、本・新聞・雑誌というアナログ利用を行う学生の国語の成績が高いことは分かった▼いま小中学校などでは、紙の教科書以外に必要に応じてデジタル教科書が併用できるようになった。その良し悪しは、これからの導入結果で分かる。今後のゆくえをしっかりと注視していきたい。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS