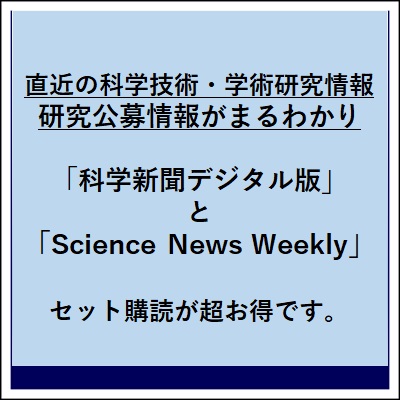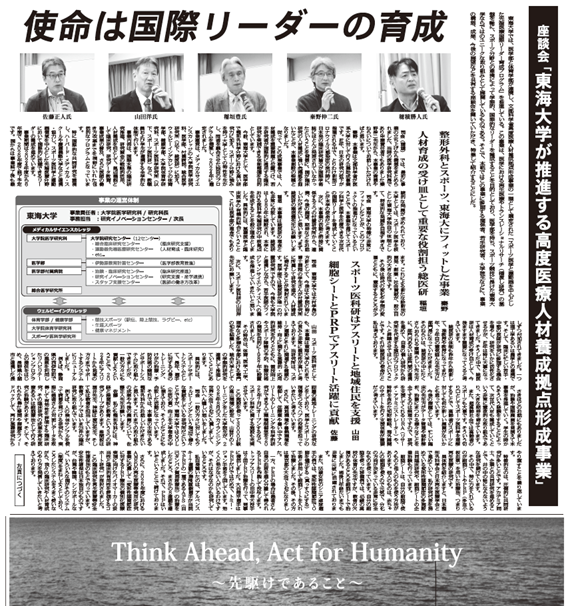日本顕微鏡学会が幕張メッセ国際会議場で開催された。正会員1474人、学生会員127人という小規模な学会だが、学術講演会の参加者数は1000人を超えている。会員の約3分の2が参加するというアクティビティの高さは、材料系、生物系、装置開発系という異分野の産学の研究者が一堂に会することで、新たな発見とイノベーションに結びつく確率が高いからだ▼ものを「見る」というのは、現象を理解する上で欠かせない。例えば、今週号の1面に掲載した細胞内のαシヌクレインを生体脳で可視化した成果は、パーキンソン病やレビー小体型認知症の本態解明や治療薬開発を本格的に進めるための第一歩となるものだ▼顕微鏡の歴史は古く、11世紀頃には研磨されたレンズが見つかっているが、電子顕微鏡となると1930年のドイツのベルリンで開発されたものが最初だ。日本ではその9年後の39年に磁界型透過電子顕微鏡が開発され、現在も大阪大学の総合学術博物館に保存されている。今回、第1回顕微鏡遺産の一つに認定された(顕微鏡遺産は15件)▼6月4日に開かれた懇親会には、エヴァ・オルソン博士(昨年のノーベル物理学賞選考委員長)も参加するなど、日本の顕微鏡の科学や技術は国際的にも高く評価されている。一方、昨今の研究力低下の原因となっている研究環境の劣化に対しては多くの大学関係者からの不満の声が尽きない。懇親会の挨拶で、岡部繁男会長(東京大学医学研究科教授)は、顕微鏡遺産が生まれた頃に比べれば、恵まれた研究環境になっており、嘆くのではなく、置かれた環境の中で努力や協力することの大切さを訴え、大きな拍手を浴びた。高い志を持つことが重要だ。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS