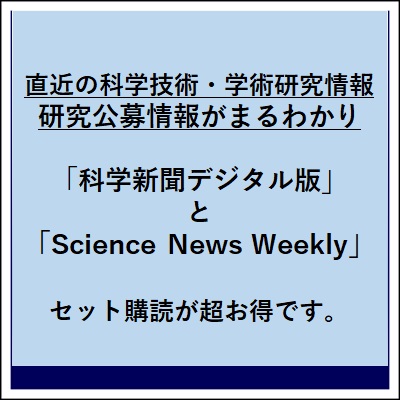国立大学は、例えば、労働安全衛生法へ対応するために実験施設・設備の整備・更新が必要になり、また労働契約法や労働法への対応によって経常経費が増加するなど、国立から国立大学法人へと設置形態を変更するだけで、大幅にコストアップした。それに加えて、2004年度から毎年1%ずつ運営費交付金が削減されつづけ、2013年度に下げ止まるまで、約1,500億円が削減された。一方、競争的に配分される研究費や大学改革関係補助金などが次々と生まれ、また従来からの科研費などの競争的資金も増加していった。
その結果、かつて各教員に配分されていた基盤的な経費は減少し、多くの研究者が「科研費を獲得できなければ、学生の教育にさえ支障をきたすことになる」と指摘するように、競争的研究費を獲得しなければ、研究室運営もままならなくなってしまった。さらに、東京大学でさえ運営費交付金の金額が人件費を下回り、多くの地方大学では、定年退職後の教員ポストを補充できずにいる。
しかし財務諸表からは、経常収益は2兆4454億円(2004年度)→3兆1293億円(2015年度)に増加しているではないか、運営費交付金は減っているが、競争的資金と合わせれば増加しているではないか、と財務省は指摘する。しかし、個別のプロジェクト研究費が増えたところで、それを目的外の研究や教育に使いことはできないし、間接経費も最大で30%に抑えられているため、学内環境を大幅に改善することは難しい。電子ジャーナルの高騰など、外的要因によるコストアップが経営を圧迫している。収益の3分の1は附属病院収入(国立大学全体)であり、病院を持たない大学はさらに厳しい経営を強いられている。
世界中で熾烈な競争が行われている科学、技術、イノベーションの世界において、大学の役割はますます重要になっているにも関わらず、日本の大学が置かれた現状は厳しいものがある。
一方、ドイツでは、連邦と州による研究・イノベーション協約が2005年からスタートし、マックス・プランク協会、フラウンホーファー協会、ヘルムホルツ協会、ライプニッツ協会、ドイツ研究振興協会に対する拠出額を、協約第1期(2005~2010年)は毎年3%、第2期(2011~2015年)は毎年5%、第3期(2016~2020年)は毎年3%、それぞれ確実に増加させてきている。研究システムの発展、ネットワーク化、国際戦略、経済界との関係構築、人材の獲得という5つの目標を掲げている。結果として、研究機関は財源についての将来予測ができるため、長期の研究計画を設計しやすくなっている。
また高等教育協約も連邦と州で結び、第1期(2007~2010年)、第2期(2011~2015年)、第3期(2016~2020年)と3期にわけた上で、2007年から2023年までの支出額として、州が183億ユーロ、連邦が202億ユーロを支出することを約束し、実際に大学には安定的に資金が拠出されている。さらにEUの研究資金についてもドイツは多く獲得している。
このように、ドイツでは、大学に対して安定した資金拠出が行われていると同時に、ファンディング機関や産学連携を進める機関、国際連携を応援する機関などへの支出を増やしてきた。
こうした彼我の政策の違いの結果、日本の競争力はどのように変化したのか。
2003~2005年に出版された論文と、2013年~2015年に出版された論文で比較すると、日本のトップ10%論文(分野別被引用数上位10%)全体では5位から10位に世界順位を下げている。分野別で見ると、ノーベル賞を多く獲得している化学分野でも3位から5位に、日本が得意と言われている材料科学でも3位から6位に、物理学も4位から6位に、その他、計算機・数学が9位から13位、工学が6位から13位、環境・地球科学が11位から13位、臨床医学が8位から10位、基礎生命科学が5位から11位へと、それぞれ順位を落としている。
一方でドイツは、中国の躍進によって、3位から4位へと順位を下げたが、分野別では多くの分野で上位5位以内に入っている。ドイツの確かな強さは、各分野の国際的な研究集会等に参加した多くの研究者から聞こえてくる。
日本とドイツの大きな違いは、大学への投資額ということ以上に、10年後、20年後までのことを政府として約束し、着実に実行することで、大学が安心して研究や教育、そして産学連携システムの構築などの大学改革に取り組めたということが大きい。明治維新の頃、明治政府は国家予算の3分の1を教育に投資し、それによって有為な人材を育て、日本を発展させてきた。政府には、そのことを今一度思い返して、ドイツから学んでほしい。
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS