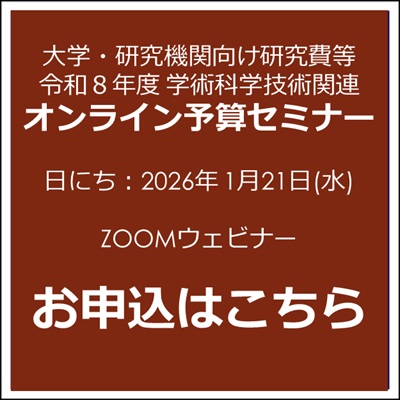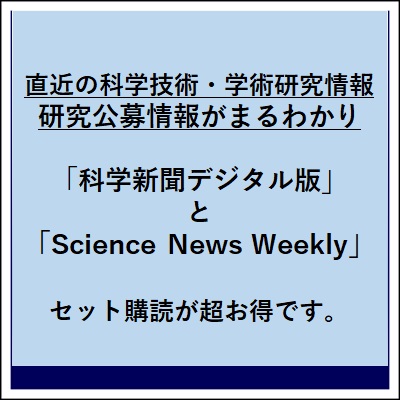2025.07.11 研究・成果
加齢で低下する造血幹細胞移植成功率 原因の一端解明 東北大など

田久保圭誉教授(東北大学提供)
東北大学大学院医学系研究科幹細胞医学分野の田久保圭誉教授(国立健康危機管理研究機構国立国際医療研究所造血システム研究部部長)、造血システム研究部の森川隆之上級研究員ら、神奈川県立産業技術総合研究所の研究グループは、白血病などの造血器疾患の根治を可能とする造血幹細胞(HSC)移植の成功率が加齢と共に減少する原因の一端を明らかにした。骨髄では血球細胞により産生されるアセチルコリンを起点とした一酸化窒素(NO)シグナル経路によって血流が保たれており、加齢によりその機能低下が見られることが判明した。また、骨髄では血流による類洞血管内皮細胞の活性化により、移植したHSCの骨髄への生着効率が維持されていた。これにより、加齢により減弱するNOシグナル経路の再活性化や、骨髄類洞血管の活性化により改善が見込まれる可能性が示された。Nature Communicationsに掲載された。
HSC移植は白血病などの造血器疾患の根治を可能とする重要な治療法のひとつで、日本だけでも毎年6000件近くの移植が行われている。しかし、未だHSC移植の適応年齢は限られており、加齢とともに増加する造血器腫瘍のリスクに十分に対応出来ているとは言い難い。その要因として、高齢者における移植関連合併症に加え、移植したHSCの骨髄への移行・生着の効率が加齢とともに減少していくことなどが挙げられる。
研究グループは、加齢による骨髄の血流動態の変容のメカニズムに着目し、それらの造血幹細胞の生着における役割を明らかにすることを目指した。さらにそこから得られた知見をもとに血流によって変化を生じる因子群を標的とし、それらに介入を加えることで加齢個体における生着率を効率的に改善する治療法の確立に挑んだ。
まず、加齢による骨髄微小環境の変化を明らかにするため、若齢マウスと加齢マウスの骨髄の代謝をメタボローム解析により比較。すると、若齢マウスと比較して高齢マウスでは血流維持に重要な、アセチルコリンを起点としNOを介したシグナルに関わる代謝物の低下や、血流低下を示すグルコース代謝産物、アミノ酸などの減少が認められた。これらの結果を踏まえ、高齢マウスと若齢マウスの骨髄の血流動態を、生体顕微鏡で測定したところ、加齢による骨髄の血流の低下が認められた。
そこでこの加齢による骨髄血流低下の原因を探るために、アセチルコリンの合成系と分解系の加齢変化を調べた。するとアセチルコリンの合成を担うコリンアセチル転移酵素は主に骨髄ではB細胞で発現していたが、その加齢変化は認められなかった。一方でアセチルコリンの分解を司るコリンエステラーゼの活性が若齢と比較して高齢マウスでは高いことがわかった。これらの結果からNOシグナル経路は骨髄血流を保つために重要な役割をしており、加齢による同経路の機能低下によって骨髄の血流が減少していることが示された。
この血流によって血液と血管壁との間にずり応力と呼ばれる力が生じているが、これを血管内皮細胞上のメカノセンサーPiezo1が感知することで血管構造の変化が促され、血管壁を通過してリンパ球が血管外へと遊走することが知られている。加齢マウスでは、このずり応力も骨髄の類洞血管血流の低下に一致して若齢マウスと比べて減少していた。一方で骨髄中の血管内から骨髄実質へのHSCの遊走は移植したHSCが生着するための重要なプロセスのひとつだ。
そこで血流中の造血幹前駆細胞(HSPC)の骨髄実質への移行しやすさの指標となる、HSPCが類洞血管壁の通過にかかる時間Δtを、生体顕微鏡を用いて高齢マウスと若齢マウスで比較した。
すると、高齢マウスではHSPCは血管壁通過に若齢マウスの2倍以上の時間がかかり、HSPCが血流中から骨髄実質への移行する効率が加齢によって低下していることが示唆された。この加齢によるHSPCの移行効率の低下は骨髄局所へのNO添加や、Piezo1活性化剤の添加などによって改善が見られた。
これらの結果から、NOシグナル経路によって保たれている骨髄の血流により、HSPCの血管外遊走能が維持されており、加齢によるこのメカニズムの低下がHSCの生着効率の低下の一因となっている可能性が示唆された。
さらに骨髄のNO―Piezo1を介した同経路が、加齢個体におけるHSCの骨髄への移行効率改善の治療標的となりうるかを探るため、加齢マウスにHSC移植を行い、NOシグナル経路や、Piezo1を活性化することで移植効率が改善するかを検証した。
まず高齢マウスに移植したHSCの短期の骨髄への移行を精査したところ、加齢によって低下したHSCの移行効率はNO投与やPiezo1の活性化剤の投与により改善が見られた。また長期ではHSC移植後の高齢マウスの生存率が、Piezo1活性化剤の投与により改善した。
これらの結果から骨髄では血球系から産生されるアセチルコリンを起点としたNOシグナル経路によって血流が保たれており、HSCの骨髄への移行が担保されていることが示唆された。
また加齢による同シグナル経路の減弱によりHSCの骨髄移行効率が低下しており、これを抑制することで高齢でのHSC移植効率が改善される可能性が示された。
今回示された知見から、骨髄の血流がHSCの骨髄への生着に関わる因子であることが新たに示された。一方でどのような機序で加齢によって骨髄中のアセチルコリンの分解系が亢進するかなどまだ十分に明らかになってはおらず、骨髄以外のアセチルコリン代謝系の加齢変化などとの連関なども考慮しながら解明してくことなどが今後の課題のひとつとなっている。
さらに、今回の知見の臨床応用の可能性などを考えると、骨髄局所でのNOシグナル経路の活性化や、Piezo1の活性化の手段などがハードルとなることも予想されることから、研究グループはこうした課題の克服を目指した取り組みを続けていくという。
© 2026 THE SCIENCE NEWS