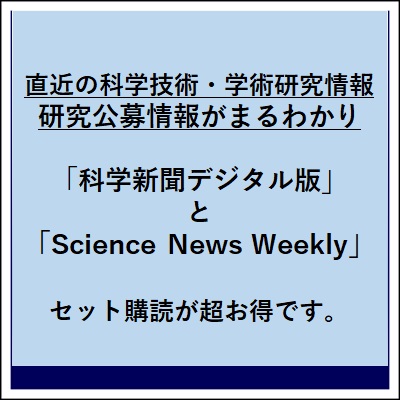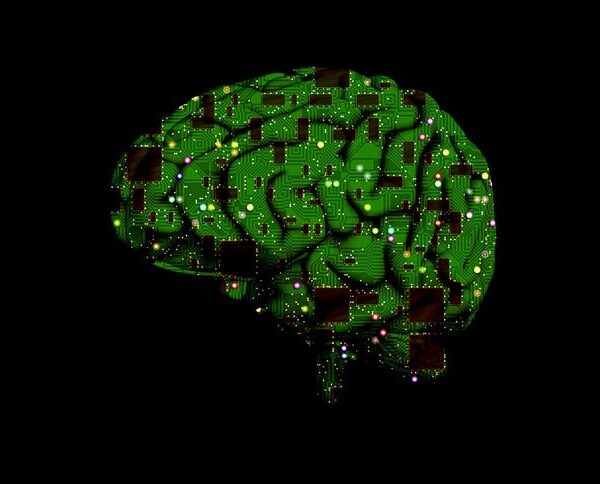2023.07.07 連載
「最先端研究とクラウド:AWSの挑戦」第2回 全方位で大学DXを進める東北大学

東北大学の青木孝文理事・副学長

次世代型研究者データベース構築
人材情報の見える化、大学経営戦略のDXをクラウドで実現
東北大学では21世紀型大学を目指して大学の全方位DXを進めている。その取り組みの中で実現したのが、アマゾン ウェブ サービス(AWS)が提供するクラウド上のデータレイクに構築した次世代型研究者データベースである。同大学のDX推進を指揮するチーフデジタルオフィサー(CDO)の青木孝文理事・副学長に話を聞いた。
「DXと言っても、人によって受け止め方は様々である。企業では、デジタルによるビジネスモデルの変革を指す場合が多い。大学も全く同じで、21世紀型の新たな大学モデルへの変革を図ることがDXだと考えている」
東北大学ではコロナ危機を受けて、2020年7月に「東北大学ビジョン2030」をアップデートし、大学変革を加速する「コネクテッドユニバーシティ戦略」を策定した。同戦略では「全方位DXを推進」「スピーディーでアジャイルな経営へ転換」「共創を加速」の3つを基本方針とし、大学における教育、研究、共創、経営の4領域の活動について包括的にDXを展開している。
2020年6月には、ニューノーマル時代のワークスタイルを変革するべく「オンライン事務化宣言」を発出。CDOおよび事務機構長の指揮のもと、学内公募に応じて全学から志願したメンバーによる業務のDX推進プロジェクトチームが活動を開始。2022年度においては、48人(男性36人、女性12人)が、16チームを構成して様々な課題に取り組んでいる。
「私は3つぐらい取り組めばと言ったが、やる気のあるメンバーばかりで、今では印鑑フリー(電子決裁や電子文書保存など)、RPA(ソフトウェア型ロボットによる業務自動化)など、16チームにも膨らんだ」と話す。平均年齢36・2歳のプロジェクトチームが挙げた昨年度の成果は、例えばRPAによる業務削減時間が前年度比25・8%増の年間10万2008時間、クラウドPBX(職場電話スマホアプリ)の利用数が83・0%増の366回線などである。その他、現在進行中の取り組みは以下の通り。
教育DXでは、多様な国籍の学生たちがメタバース空間に集う新しい授業形式の試行、オンライン国際共修授業の展開、東北大学オープンバッジの発行などに取り組んでいる。
研究DXでは、ナノサイズを見る巨大な顕微鏡である次世代放射光施設ナノテラス、15万人規模の一般住民コホート調査を行う東北メディカル・メガバンク機構、世界の災害統計の拠点である災害科学国際研究所などを中心に、データ駆動科学の推進に全学的に取り組んでいる。
共創DXでは、デジタルを活用した新たなスタイルの社会共創を展開している。現在、カーボンニュートラル時代のGXを牽引するデータ駆動型の産学共創ハブとして「東北大学サイエンスパーク」を整備中である。産業界のデジタル人材の育成にも力を入れている。
経営DXでは、業務改革、人的資本経営などに取り組んでいる。「DXの根本課題は、テクノロジーの急速な進歩に対して、組織や社会システムの対応スピードが遅くて追いつけず、差が拡大してしまうことである。やはり中心課題は人と組織であり、スピード感を持ってアジャイルに動ける大学経営を目指す必要がある」と、青木氏は大学DXのポイントを説いている。
特に人的資本経営に関するDXとして取り組んだのが「タレントマネジメント」。クラウドを活用した次世代型研究者データベースの構築である。国際卓越研究大学へ向けた構想にも活用する。大学では国際的なプレゼンスの向上や若手研究者の活躍、多様性と包摂性の促進、産学共創など、様々な取り組みが求められている。
そのためには教員の研究・教育・社会貢献など多面的活動をエビデンスベースで評価・分析して、大学の経営戦略にフィードバックすることが求められている。しかし、従来の研究者データベースや論文データベースによる分析では、研究者の包括的な活動状況を把握することができず不十分であった。
また、企業との共同研究や学生の論文指導、管理運営業務など秘匿性のある活動の情報は、研究者自身が時間を割いて学内データベースに入力してきた。しかし、入力データの量や質に差があり、エビデンスベースの評価がしにくいといった課題もあった。
これらの問題を解決したのが、データレイクによる学内外のデータの集約・統合だった。AWSのデータレイクは、様々なフォーマットのデータを集め、一元的かつリアルタイムに処理・可視化することができるのが特徴だ。そのデータレイクに、学外の論文データベース、学内の人事給与や財務会計、学務などの各種情報システムの様々なフォーマットのデータを投入。研究者自身や評価担当者が必要に応じてデータを取り出せるようにした。実際に必要なデータは学内外のどこかに存在しており、手入力はほとんど不要という考え方である。これにより、研究者の多面的でエビデンスベースの研究・教育評価が、瞬時に自動化・効率化され、可視化できるようになった。
「これまで困難とされていた大学の研究人材の見える化に取り組み、他大学に先駆けて研究者のタレントマネジメントを実現したかった。これを実現するため、スピード感を持ったアジャイルな実装に適するクラウドサービスを採用する必要があった。AWSはセキュリティの高さ、災害などに対する堅牢さ、使いやすさ、コストなどに優れており、これを実現するためには最適な選択であった」と、導入の理由を挙げている。
この次世代型研究者データベースは今年4月から本格運用が開始された。「今後も同大学のDXにはクラウドサービスを活用していきたい」と、青木氏は展望している。(了)
© 2026 THE SCIENCE NEWS