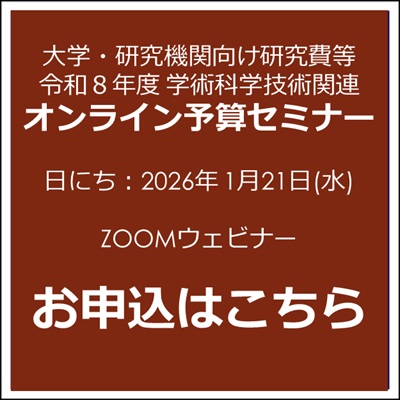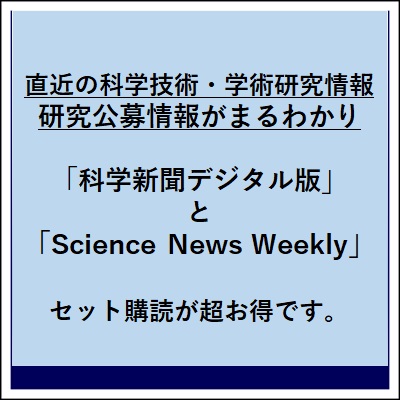TOP > コラム・素領域一覧
コラム・素領域
科学新聞の1面に掲載している『素領域』全文と、Web限定コラムをお読みいただけます。
2022年4月22日号 素領域
日本の人口の80%が新型コロナのmRNAワクチンを2回接種しており、国内外の臨床データからも、一定の感染防止効果と重症化予防効果が確認されているにも関わらず、いまだに、ワクチンは危険だから打つのはやめよう、といって駅前で主張している人々や街宣車のようなものを見る▼彼らの主張を聞いてみると「○○先生(医師)が言っていた」「とにかく怖い」といった情緒的なものが多く、論拠は非常に弱い。また「安全性が証明…
2022年4月15日号 素領域
4月5日に公表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書第3作業部会報告書では、世界全体のCO2をはじめとした主要な温室効果ガス(GHG)の人為的排出量が、依然として増え続けていることが改めて示された▼世界各国が取り組む温暖化防止対策には目標とする1・5度Cの上昇を止めるため、さらに大きな努力が求められている。気象庁の各種データ・資料から「日本の年平均気温偏差の経年変化(189…
2022年4月8日号 素領域
騒音と雑音。意味が似ているふたつの言葉だが、そのとらえ方として共通する認識は「うるさく、不愉快な音」となるだろう▼この好ましからざる音に関して科学的に興味深い研究成果が出されている。騒音についてだが、ヨーロッパの大学の研究で、騒音の大きい場所に住んでいる人は、相対的に体脂肪の量が多くなり太りやすくなるという結果が出た。騒音による刺激を受けると、ストレスによってストレスホルモンのコルチゾールが増える…
2022年4月1日号 素領域
今年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻は世界に衝撃を与え、先行きの見えない状況が続いている。国内外への避難民は1千万人を超えたという。その中で日本ユニセフ協会や日本赤十字社、国連UNHCR協会、在日ウクライナ大使館、国際NGOだけでなく、各自治体なども寄付を呼びかけ支援の輪が広がっている▼国内の大学でも複数の大学が学生等の受け入れを表明した。日本経済大学はウクライナの避難民学生の受け入…
2022年3月25日号 素領域
昨今、大学と企業との共同研究が増加しているが、多くの大学ではあまり儲かっていないようだ。これは政府の競争的資金と同じような経費の計算をしているためだという▼政府系資金では、直接経費+間接経費30%が研究費総額として計上される。つまり直接経費が1000万円であれば、総額は1300万円。一方、産学共同研究の場合、直接経費の中に関わる教員や学生の人件費を含めることができる。しかも教員の人件費は能力や実績…
2022年3月18日号 素領域
21世紀に入ってもなお、人類は互いに国益などで争い武力による争いを続けている。第2次世界大戦で、多くの国のたくさんの人々が命を失ったが、その後も戦争はなくならず、地域紛争やテロが相次いで起きている▼今回のロシアによるウクライナ侵攻では、ロシア側が核攻撃をもにおわせて不気味な状況となっている。しかし、核攻撃は絶対に現実になってはいけない、人類最大の脅威である▼世界の主要国の一つであるロシアの大統領が…
2022年3月11日号 素領域
発生からしばらく経過したが、1月15日に南太平洋のトンガ諸島で大規模な海底火山の噴火が起きた▼噴煙は高度3万㍍に達し、半径260㌔に広がった。その爆音たるや南太平洋全域に及び、トンガから800㌔離れているフィジーの首都スバでも、雷鳴のようにとどろいたという。テレビの映像での印象ではあるのだが、その規模の大きさは想像に余りある。噴火の影響により15㍍以上の津波がトンガを襲い、日本でも岩手県や鹿児島県…
2022年3月4日号 素領域
カメラやセンサーの小型化・高感度化に伴うバイオロギングの発展は目覚ましく、これまで知られていなかった野生生物の生態が明らかになってきている。バイオロギングは野生生物に小型の行動記録計(データロガー)やGPS装置などの機器を装着し、その動物の生態や周囲の環境情報を記録する手法で、動物を捕獲して回収したり、機器のみを回収したりすることによって人間が観察することのできる範囲外の情報を取得できる▼最初は主…
2022年2月25日号 素領域
ムーンショット目標を見直すことも含めて考えなければならない。CSTI有識者議員会合で量子技術イノベーション戦略の見直しについて、議論する中で出てきた▼ムーンショット型研究開発制度は、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象に、野心的な目標(ムーンショット目標)を国が策定し、プログラムディレクター(PD)が複数のプロジェクトマネージャーを選定して、目標達成のための研究開発を進め…
2022年2月18日号 素領域
オミクロン株の登場で、またもや急速な感染拡大に陥っている新型コロナウイルス。2年以上続くこのパンデミックは、いまだに全く先が見通せない。世界が一致協力して対策に力を注がねばならない▼しかし、そうした中で北朝鮮のミサイル発射実験が続き、欧州に目を向ければロシアによる侵攻が危惧されるウクライナ問題が緊迫した局面を迎えるなど、世界情勢は雲行きが怪しくなっている▼世界がいま抱える目前の危機は、パンデミック…
2022年2月11日号 素領域
ガンの早期発見のための診断はバイオプシー(生検)によって行われる。一般的に腫瘍のある組織を取ってきて病理専門医が顕微鏡で判断するわけだ▼最近では、血液や尿などからガンを検査する方法(リキッドバイオプシー)が身近になってきている。これはガンが体のどこかにできると、血液の中に特徴的に作られるタンパク質などの物質が増えることを利用して診断する。腫瘍マーカーと呼ばれる。例えば、前立腺の検査で、PSAが高い…
2022年2月4日号 素領域
今年の立春は2月4日。寒い日はまだ続くが暦の上では春の始まりを意味し、関東でも既に梅(白梅)が咲き始めている。気象庁によれば今年関東で最初に咲いたのは銚子(千葉県)の梅で昨年より6日遅い開花だった。とはいえ毎年最も早く咲く那覇(沖縄県)では12月30日に開花していて、前年より1日、平年より14日早かった▼春は花粉症のシーズンの到来でもある。日本気象協会によれば関東・甲信では少ないながらも既にスギ花…
2022年1月28日号 素領域
日本学術会議のより良いあり方とは何か? CSTI有識者議員懇談会が報告書を取りまとめた。ただし、まとめというにはまとまりのない内容になっている▼学術会議会員任命拒否問題をきっかけに、学術会議のあり方について検討が始まり、自民党PT、学術会議ともに報告を取りまとめ、政府としての改革の方向性を決めるため、CSTI有識者議員での議論が9回非公開で行われてきた。これまでの議事概要を見ると、科学的助言機能の…
2022年1月21日号 素領域
「医食同源」ということばがあるように、食事は我々の健康に欠かせない大切なものである。今年も食べた人がいるだろうが、新年1月7日の朝食に食べる七草粥の習慣なども、健康を願う昔の人の知恵だろう▼農林水産省「数字で見る日本の食(2018年度食育白書から日本の現状を紹介)」によれば、第3次食育推進基本計画において、食事面で健康のためにするよいこととして、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ…
2022年1月14日号 素領域
令和4年がスタートした。多くの人が神社仏閣の前で、あるいは山や海で初日の出を仰いで、「今年1年、幸せな日々を送れますように」と祈ったことだろう▼幸せになりたい。誰しも思うことではあるが、そう願うならば、よく知られた「情けは人のためならず」ということわざを思い起こしてほしい。この言葉の本来の意味は「人に情けをかければ、その人のためになるばかりでなく、巡り巡って自分のためになる」ということである。これ…
2022年1月1日号 素領域
謹んで新年をお祝い申し上げます。旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます▼新型コロナウイルス感染症は日本では沈静化しているものの世界的な拡大は衰えをみせない。新規感染の平均報告数が最多の米国では、これまでに81万人が同疾患で死亡し、日本では1万8千人余りが死亡した。沈静化の理由が不明なまま日本でも新たな変異株が拡大している▼Agoopに…
2021年12月17日号 素領域
この原稿を書いている時点で57の国と地域で感染が確認されるなど、オミクロン株が世界的に広がっている。オミクロン株は、これまでの変異株とは異なる変異をしており、ワクチンの感染予防効果が低いなどと言われている▼どうしてこんな変異株が生まれたのか。専門家から話を聞くと、2つの要因があるようだ。一つは、アフリカにおけるワクチン接種率の低さ。国によって異なるが、1~2割という接種率の中で新型コロナウイルスが…
2021年12月10日号 素領域
岸田文雄首相は10月8日の第205回国会における首相就任後初の所信表明で「新しい資本主義」の実現を政策目標の一つに掲げ、それを実現する車の両輪の一つである成長戦略における第1の柱に「科学技術立国の実現」を据えた▼実現へ向けて実のある政策を進めてほしい。その具体策の一つとして、世界最高水準の研究大学を形成するために10兆円規模の大学ファンドの年度内実現をあげており、その準備がいま進行中である▼かつて…
2021年12月3日号 素領域
生物の進化の仕組みの中で重要な説として考えられているものに、自然淘汰と適者生存がある▼自然淘汰とは、自然界で生態的条件や環境などによりよく適合するものは生存を続け、そうでない劣勢のものは自然に淘汰されること。一方、適者生存は、環境に最も適応できる生物だけが生き残り、適応できない生物は滅びていくということである▼ウイルスは、他生物の細胞を利用して自己を複製させる、ごく微小な感染性の構造体である。生命…
2021年11月26日号 素領域
啓蟄は虫が春を感じて冬ごもりから出てくる時期だが、その逆の虫が冬ごもりする時期は閉蟄と言い、旧暦10月上旬頃を指すという▼昆虫は変温動物であるため、気温が下がると活動できなくなる。一方で恒温動物より低温下の生存という面では寒さに強く、多くの場合凍結しなければ休眠することで冬の厳しい季節に耐えることができる▼昆虫は恒温動物より高温には弱いが、一般的に幼虫であれば10度C以上で発育し、成虫であれば10…
コラム・素領域 最新記事
© 2026 THE SCIENCE NEWS