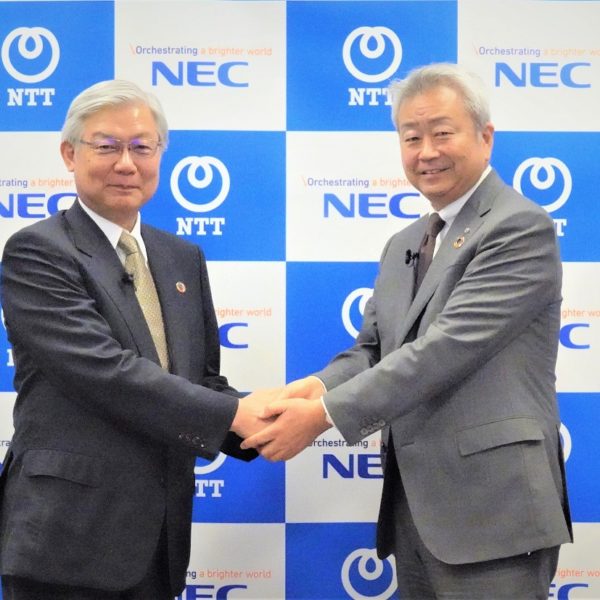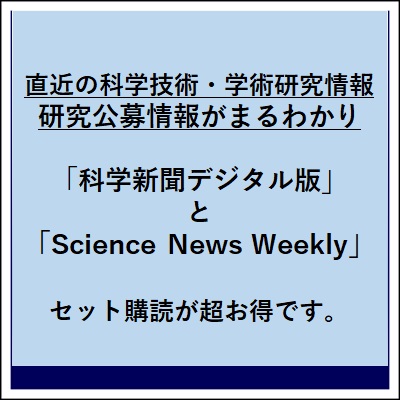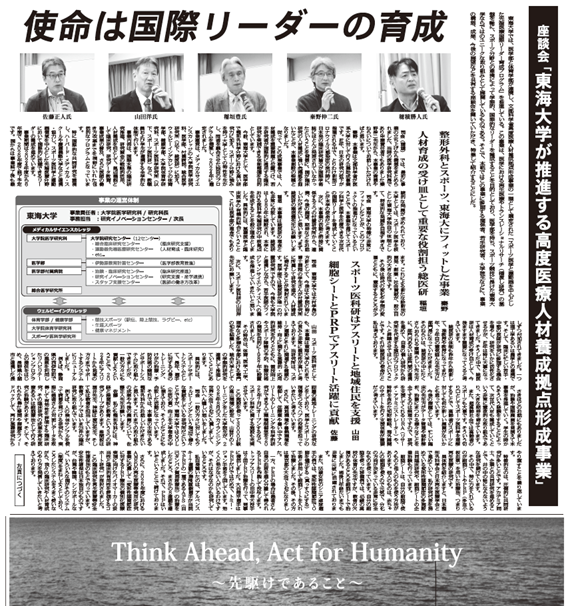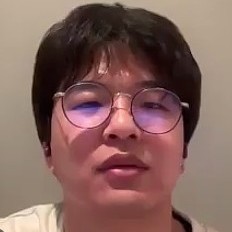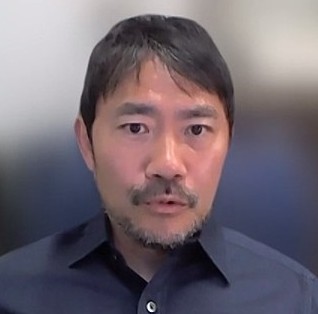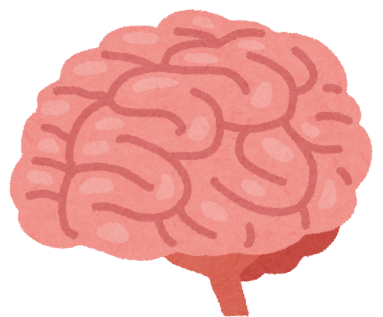TOP > 最新記事一覧
最新記事
科学新聞に掲載されている記事の一部をお読みいただけます。
各種キーワードごとに記事を絞り込むことも可能です。
2020.07.10
大学等
2020.07.10
研究・成果
2020.07.10
研究・成果
2020.07.03
政策
「コロナ後に攻勢 社会のデジタル化推進」政府のイノベーション戦略概要
第6期科学技術基本計画の初年度となる2021年度予算の重点項目が明らかになった。政府の統合イノベーション戦略推 […]
2020.07.03
研究・成果
2020.07.03
研究・成果
2020.06.26
政策
2020.06.26
政策
2020.06.26
研究・成果
「農業生態系をデジタル化」理研・福島大など成功 持続的な作物生産に期待
理化学研究所バイオリソース研究センターの市橋泰範チームリーダーと福島大学食農学類農業生産学コースの二瓶直登准教 […]
2020.06.26
研究・成果
2020.06.19
産業・製品
2020.06.19
研究・成果
2020.06.19
研究・成果
2020.06.19
研究・成果
© 2026 THE SCIENCE NEWS